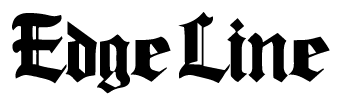大阪・関西万博の大屋根リングを設計した建築家・藤本壮介氏が10月8日に大阪・関西万博内のテーマウィークで2025年日本国際博覧会 テーマウィークプログラム『共鳴と森-突き破る塔(1970)から開かれる空(2025)へ』トークイベントに出席。横山英幸大阪市長、静けさの森の植栽などを担当したランドスケープデザインディレクター・忽那裕樹氏とともにトークを繰り広げ、テーマ事業プロデューサーの宮田裕章氏が司会を務めた。
本トークショーでは大阪・関西万博を通じて築いてきた価値や取り組みの意義、そしてそれを未来へとつなぐための活動についてを話すというもの。
リングの全周は約2キロ、高さは外側で最大約20メートルという巨大な大屋根リング。藤本氏は完成前と完成後、実際に人が入ってきてからの心境を順を追って話していくことに。「僕らは会場を作る仕事なのでゆっくりできあがっていく様子を見ていたんです。もちろん自信を持って作ってたんですけども、初めて大勢のお客さんが入ってきて、本当のところどういうふうに受け止められるのかっていうのは、ちょっと怖かったわけです」と心情を吐露。
その藤本氏が抱えていた“怖さ”について宮田氏も、「本当にあのリングがすごいかどうかって、万博開幕前全く伝わらなかったんですよね。藤本さんは、『開幕すれば絶対伝わるはずだ』って言ってて」と思い出して、しみじみ。
そんな気持ちを抱えたまま4月13日の開幕日を迎えると「ばーっと人が入ってきて、なんかみなさん楽しそうな感じで。そんな楽しそうな雰囲気が会場を満たしていって、そこに命が吹き込まれていったような感じがしたんです。あれが1番僕にとっては感動的でしたね。リングも、もちろん構造体としてはできてたんだけど、物なのに感動するというよりは、そこに人が来て、リングの3階を人が歩いてるわけですよ。あの絶妙な距離感。こっちは、楽しそうな顔をして歩いてる顔が見える。向こう(対面)側を見るとなんか、ああ、人が、ああ歩いてるなって。遥か彼方なんだけど、同じところにみんないるなっていう感じがして。だからね、設計の意図とかあらゆること考えてた通りだったんだけど、でも、それを遥かに超えてそこに現れた時に、こういうことなのか、万博っていうのは……っていう風に感動しましたね」と、初日の感動を語る。宮田氏も「あの場にできて、空間で立ち上がった体験に一旦感動するんですけど、来場者が入るともう一段上がりましたよね」と、より気持ちが高ぶったそうだ。
その屋根の下の設計の狙いについても触れ、「巨大なんだけど、下でみんな地面に座ってお弁当とか食べてるじゃないですか。あれ、何でかって言うと柱が3.6メートルの間隔で置いているんです。3.6メートル×3.6メートルって大体8畳間ぐらいの大きさなんですよ。しかも上に梁(はり)が入っているところの下にみんな座っていて、そうすると、なんかおうちの中にいるような感じがする安心感。でも、その隣の上から抜けてるところは、大聖堂みたいにずっとこう果てしなく繋がってくみたいになっていて。だから、あの構造体の中は実はすごく安心できる。ヒューマンスケールと見たことないような巨大スケールが実は同居しているんです」と、解説。
そうした人の気持ちまで考えての設計は精神科医の父親の影響だそうで、「人に寄り添うっていうのは大前提なんですが、今回の場合は万博ならではの、『ああ、やっぱりすごいな、日常ではなかなか味わえないな』っていう、その体験も両方重要」という。そうした“両方重要”な部分を、今後のまちづくりへ「どう共存させて作っていくのかっていうのは、たぶんこれからのまちづくりの一番の鍵なんじゃないかなと思うんです」と、展開していた。
トークの第3部では、藤本氏、宮田氏、森と共鳴する「Better Co-Being」の建築を担当した SANAA(妹島和世氏、西沢立衛氏)の4人でトーク。その際に妹島氏からの大屋根リングの評価を直接言われたことがあるそうで「お会いすると言われるんですが、『硬い、でかすぎる』と言われるんです(苦笑)」と率直に言われるのだとか。とはいえ、藤本氏にも“言い分”があるそうで「建築を超えたものを万博のシンボル的にして、建築のことを知らなくてもあそこに国が集まっているんだというシンプルな真円にしていて、真円って硬い形なんです。妹島さんはもしかしたら賛同してくれないかもしれないけれど、(藤本氏自身としては)硬いのはしょうがない、硬いのは前提で、近くに行くとだんだん硬くなくなって、だんだんほぐれていくという作り方をしているんです」と、申し開きもしていた。
ほかにも、本日のトークを通して藤本氏は「淀川に浮かぶ公園を作りたいなと思いました」と、アイデアが浮かんだようで、次々にその案を宮田氏らと膨らませて楽しんでいた。
取材・撮影:水華舞 (C)エッジライン/ニュースラウンジ